家を建てるとき、よく耳にする「建築面積」という言葉。建築に関わる法律や設計図でも必ず登場しますが、実際にはどのような意味を持っているのでしょうか?
建築面積の定義とは?
建築面積とは、「建物が地面に投影された水平面積」のこと。簡単に言えば、建物を真上から見たときに、地面に影を落とす範囲の広さです。
- 建築基準法で明確に定義されており、建ぺい率の計算にも使用されます
- 屋根や庇(ひさし)が1m以上出ている場合は、その面積も建築面積に含まれます
- 地下室や2階部分は含まれませんが、外に張り出したバルコニーなどは条件によって含まれることがあります
建築面積の使われ方
建築面積は、都市計画や建築許可の判断にも大きな影響を及ぼします。
- 建ぺい率=建築面積 ÷ 敷地面積 × 100(%)
- 建ぺい率によって、敷地内にどのくらいの広さの建物が建てられるかが決まります
- 住宅密集地では建ぺい率が低く設定されていることが多く、広すぎる建築面積は法律上NG
実際にどう活用する?
例えば40坪の土地に家を建てたいとき、建ぺい率が50%であれば、建築面積は20坪以内に抑える必要があります。設計士はこの制限の中で、効率的かつ魅力的な住まいづくりを工夫します。
まとめ
建築面積は、住まいの「かたち」を決める重要な指標です。これを理解することで、自分の理想の家がどんな規模・デザインで建てられるのかを具体的にイメージできるようになります。

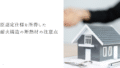
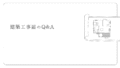
コメント